カクテル(Cocktail)とは、、、
お酒にジュースや果汁などを混ぜ合わせた飲料となります。
お酒+何か=カクテル
カクテルという言葉の使用が初めて確認できたのは、
1806年5月13日アメリカの新聞紙「バランス・アンド・コロンビア・リポジトリ」に
カクテルの定義が掲載されていたのが始まりだと言われています。
このことにちなんで5月13日はカクテルの日となり、現在ではカクテルのイベントなども行われています。
語源
カクテルの語源には様々な説があります。
有名なものでも5つはありますが、
IBA(国際バーテンダー協会)が定めているのはメキシコ、
カンペチェの「コーラ・デ・ガジョ(雄鶏の尻尾)」説です。
英語にすると「テール・オブ・コック」
これが「コック・テイル」「カクテル」となりました。
混ぜ合わせた液体自体は古代から作られていたのですが、
カクテルとは呼ばれていませんでした。
ですが液体を入れる為の様々な形のリュトン(角杯風の器)、
古代ギリシャでは「混成器(クラテル)」と呼ばれていました。
そしてこれは持論ですが、
混成器(クラテル)はワインと水を混ぜ合わせる器の役割を果たしていました。
この「クラテル=液体を混ぜ合わせる」という認識の言葉が現代まで伝わり、
カクテルとなったとではないかと僕は思います。
もしかしたら僕が知らないだけで、
この説は誰かが提唱しているかもしれません、
知ってる方は是非教えてください^^
カクテルの分類
カクテルは大きく分けて2種類、
ショートタイムカクテルとロングタイムカクテルです。
違いとしてはカクテルの度数と美味しく飲める寿命です。
- ショート度数高め、寿命は10分~15分。
- ロング度数低め、寿命15分~20分。
つまり、出来立てが最高の状態という事です。

Gert_Lapoehn / Pixabay
■ショートカクテル
シェイクやステアという技法を使い、
お酒とお酒を混ぜ合わせる、冷やす、飲みやすくする、
加水、香りを出す役割を果たし仕上げます。
時間をオーバーすると、氷が入っていないのでぬるくなり飲みにくくなります。
また飲み方としてはボディの部分ではなく、
ステム(脚)の部分を持つと指の温度が伝わらずに済み、冷たいまま飲めます。
国際的なマナーとしては、ワインに多いですがボウル(ボディ)の部分を持ちます。
社交場なので人が多く、こぼしたり人にかけないようにする為です。
もちろん液体の温度は上がりますが、味わうよりも、人に迷惑を掛けない方が優先されます。

2007495 / Pixabay
■ロングカクテル
ビルドやシェイクという技法を使用します。
グラスにそのまま液体を注ぎ混ぜ合わせたりするスピーディーに提供できるカクテルです。
ショート同様時間をオーバーすると分離し氷が溶け、水っぽくなります。
グラスの持ち方は下の部分を持ち、
小指をクッションにしてスッと置くと音が全然鳴らないのでスマートです。
■スタンダードカクテル
スタンダードカクテルとはどこのバーに行っても注文できる有名なカクテルです。
ジントニック、モスコミュール、モヒート、マルガリータなど聞いたことのある名前が多いかと思います。
お店によって、作り手によって同じカクテル同じレシピでも味が違います。
その違いは何なのか。これがバーの面白いところです。
味を構成する要素はいくつかあります。
お店の雰囲気、空気感、匂い、BGM、ベースに使うお酒の種類、分量、
レモンライムの酸味具合、氷の状態、グラスの種類、口当たりの感覚、
作り手のコンディションと飲み手のコンディション、精神状態、舌の状態、作り手のフィルター(外見)、
所作などなど、様々な要素で味が構成されていきます。
もちろんこれはバーテンダーの仕事なのでベストな環境作りをして、
お客様に不自然に感じさせないでフラットで楽しんで頂くのがなによりです。
バーテンダーは美味しいと感じさせる要素も大事ですが、
美味しくないと感じさせる確率を下げた方が効率は良いです。
以上になります。
ご覧頂きありがとうございました。











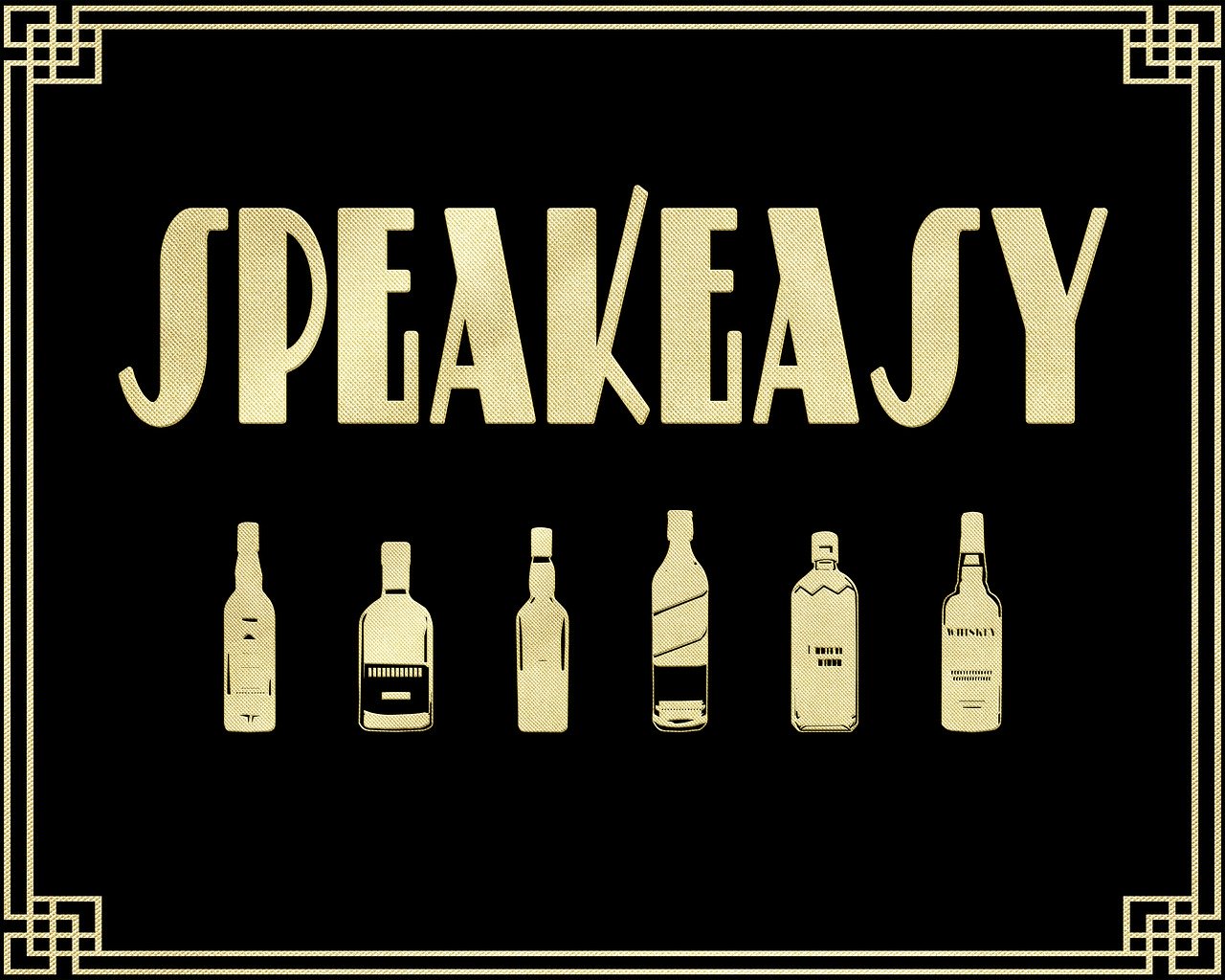



コメントを残す